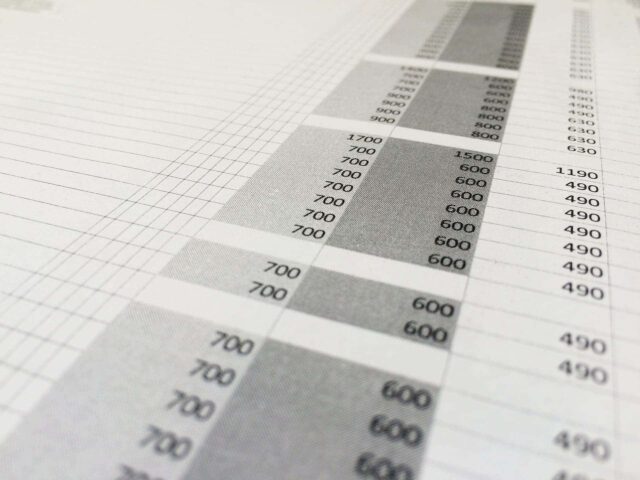- 2023年6月13日
「50歳で転職する自信がない…」――。
そんな不安を抱える方は少なくありません。
リクルートの『ミドル世代の転職動向について2024』によれば、50代の転職は2014年に比べて約6倍に増加しています。数字だけを見るとチャンスは広がっているように見えますが、いざ自分のこととなると「何をしたいか分からない」「年収が下がるのが怖い」「本当に採用されるのか…」と立ち止まってしまう人が多いのではないでしょうか?
私自身も同じでした。20年近く働いた会社は居心地も良く、年収が下がったからといってすぐに辞めるつもりはありませんでした。でも「この先10年、年収が下がり続けたら?この環境で成長できるのか?」と自問自答したとき、ようやく転職を決意しました。
ただ最初は「転職活動をするぞ」と決めただけで、業界も職種も定まらず、やりたいことが明確ではなく迷い続けました。
そんなときに役立ったのが、次の4つの視点です。
- 経験(今までのキャリアをどう横展開できるか)
- 年収(現実と希望のバランスをどう取るか)
- 将来(10年先まで通用するキャリアか)
- 成長(学び続けられる環境か)
さらにAIが「壁打ち相手」として転職活動のパートナーとして大活躍してくれました。AIには答えを求めるのではなく、問いを投げかけ、その回答をもとに再び考える。このラリーを繰り返すことで、頭の中が整理され方向性・やることが明確になっていったのです。
AIは私の転職活動にとって、なくてはならない存在になりました。
ここでは、私のAIを使いながらの50歳の転職活動体験談をご紹介します。
キャリアの横展開、今までの経験をどう活かすか?
工夫のポイント
- 「やりたくないことリスト」を作る
- これまでの経験を、異業種でも使える形に言い換える
- AIに「この経験はどんな業界で活かせる?」と質問してみる
私の体験談:EC業界からコンサルへ
私はECサイトの運営やWEBマーケティングの仕事を長年続けてきました。直近はアパレル業界でしたが、「また同じことを繰り返すよりも、新しいことを学び、成長したい」という気持ちが強く、思い切って「やりたくないリスト」の一番上にECサイトの運営を入れました。
最初は、これまでの経験を活かして戦略コンサルタントに挑戦したいという気持ちがありました。ところが転職エージェントに相談した際、「戦略コンサルは未経験から入るのは相当ハードルが高い」と言われました。正直ショックでしたが、自分では気づいていなかった現実を受け止めるきっかけになりました。
そこで改めて、過去の実績を棚卸ししてみると、ECサイトに関連するシステム導入や移管、プロジェクト推進の経験が多くあることに気づきました。エージェントとも話し合いながら、ITコンサルタントやプロジェクトマネージャーのようなポジションなら、現実的にチャレンジ可能であり、かつ成長もできる道だと判断しました。
これが私にとっての「キャリアの横展開」の第一歩になったのです。
あなたのキャリアも「横展開」できる
キャリアの横展開とは、「軸を少しずらして、これまでの経験を別分野に応用すること」です。
たとえば、以下のようなケースがあります:
- 営業職→ 顧客視点を活かして「カスタマーサクセス」や「導入支援」へ
- 事務職→ 調整力や社内連携の経験をもとに「業務改善コンサル」や「PMO」へ
- 接客業→ ユーザー視点を活かして「UXリサーチ」「カスタマーサポート設計」へ
自分では「普通の経験」と思っていても、違う分野から見ると貴重なスキルに変わることがあります。
私はAIに自分の職務経歴書をアップロードし、「この経歴だと、どんな仕事に活かせる?」と質問を投げかけました。
すると、自分では気づかなかった業界や職種のヒントが返ってきて、「そうか、こういう形でも自分の経験は使えるんだ」と視野が広がっていきました
まずは「やりたくない」を明確に
「何がやりたいか分からない」と感じている方は、まず**「やりたくないこと」から明確にする**のがおすすめです。やりたくない理由を言語化すると、自分が本当に大事にしたい価値観や方向性が見えてきます。
「横展開」は、必ずしも華やかなチャレンジである必要はありません。
自分の経験を、少し角度を変えて活かせる場所を見つけるだけで、道は開けていくと私は感じました。
転職の目的を明確に、自分と企業の視点を俯瞰で見る
工夫のポイント
- 年収だけで判断せず、「年収 × 成長機会 × 働きやすさ」で総合的に検討「自分はいくらで雇われる価値があるか」を客観視してみる
- 企業は“将来回収できる投資先”として人を見ている
体験談
転職活動を始めた当初、私は「年収を目標年収まで上げたい」という気持ちが強く、希望年収を下げることに大きな抵抗がありました。
初めて最終選考まで進んだ企業に対し、希望年収を提示したところ、面接官から「原燃州都と希望年収のギャップの根拠は?」と聞かれました。
私は「これまでのキャリアに自信があり、この希望年収で十分に価値を提供できると考えている」と答えましたが、結果は不合格。手応えがあっただけに、大きなショックを受けました。
転職活動では、落選が続くと自己肯定感が下がってしまいます。過去のキャリアそのものを否定されたような気持ちになり、心が折れそうになる瞬間もありました。
そんな時、友人からこんな言葉をかけられました。
> 「企業は“過去の実績”より、“これから何をしてくれるか”を見てるんじゃない?
> 50歳にポテンシャル採用なんてないよ。即戦力になれないと判断されたんじゃないかな」
その言葉に、ハッとさせられました。
私は“自分の価値=過去の実績”だと思っていたし、転職に“成長・チャレンジ”を求めていました。企業は50歳の採用を「未来への長期投資」ではなく、「短期投資で即回収」として人を見る。50代に求められるのは、まさに即戦力。
そこからは、「入社後すぐにどう貢献できるか?」という視点で、自分の経験やスキルを伝えるようにしました。
また、年収に関しても「現年収よりここまでは上げる」を目標に、現実的なラインに見直しました。
「まずは入社して成果を出し、その後に希望年収へ到達する」という逆算スタイルにシフトしたのです。
さらに、入社時の年収だけでなく、「その企業でどれだけ成長できるか」「将来のステップにつながるか」といった視点も重視するようになりました。
特に50代の転職は、“これが最後の挑戦かもしれない”という覚悟があるからこそ、「この先10年、自分はどうありたいか?」を軸に決断することが大切だと実感しました。
読者へのアドバイス
企業側がどんな視点で年収を決めているかを理解することで、自分の希望条件とのギャップを埋めやすくなります。
たとえば、AIに職務経歴書を読み込ませて「このスキルでどの程度の年収が妥当か?」と聞いてみるのもひとつの方法です。
また、転職の選択肢を“年収維持”だけに絞るのではなく、「新しい環境での学び」「柔軟な働き方」「心地よい人間関係」など、自分にとっての価値の軸を複数持つことが、納得感のある決断につながると感じました。
10年先を見据える(60歳以降もプラスになるか)
工夫のポイント
- 「今の選択が60代の自分にどんな影響を与えるか?」を基準に考える
- スキル・人脈・経験の“資産化”という視点を持つ
- 定年や再雇用ではなく“自分が働きたい形”を逆算してみる
体験談
50歳の転職は、ただ“次の会社を決める”だけでなく、「60歳以降の働き方をどう築いていくか」の土台作りだと感じました。
だからこそ私は、「この転職によって、60歳以降にどんなスキル・経験が残るか?」「この会社で働く10年が、自分のキャリアにどういう意味を持つか?」という長期的な視点で企業選びをしました。
例えば、60歳で再び転職することを考えると、体力面・年齢の壁・市場価値…どれをとっても今より厳しい。ならば今の選択こそが、“将来の自分を助ける準備”になるはずです。
私自身、今回の転職では未経験のITコンサルにチャレンジしました。
正直、即戦力で入社するのは簡単ではなく、不安もありました。でも、ここで学んでおけば「業界知識・プロジェクト管理・ITスキル」が手に入る。これらは60歳以降も活かせると考えたのです。
また、「どんな働き方をしたいか?」という視点でも考えました。私はこの先、場所や時間に縛られない柔軟な働き方をしたいと思っています。そのためには、リモートで通用するスキルやマネジメント経験を積んでおく必要がありました。
だからこそ、「年収」「条件」だけではなく、「この仕事を通じてどんなスキルや働き方を得られるか」という“未来志向の判断軸”を持つようにしました。
読者へのアドバイス
転職活動では、目の前の条件や不安にばかり意識が向きがちですが、「10年後の自分にとってプラスになる選択か?」という軸を持つことが、後悔しない選択につながります。
たとえば…
- この会社で学べることは、60代の働き方に活かせるか?
- この職種は年齢に関係なく働けるスキルになるか?
- この人たちと築ける人間関係や信頼は、自分の財産になるか?
こうした問いを自分に投げかけてみてください。
「今の決断が“未来の自分”にどんな資産を残せるか?」という視点で考えることで、単なる転職ではなく、“キャリア戦略”としての選択ができるようになります。
50歳でも成長したい、学べる環境かどうか
工夫のポイント
- 「学び続けられるかどうか」は、50代転職の満足度を左右する重要な要素
- 静かな退職(挑戦が止まり、惰性で働く状態)に陥らないための“刺激”があるか
新しい領域・技術・業界に触れる機会があるかどうかを面接や求人情報から読み取
体験談
前職では、ある時から「自分は成長していないな」と感じるようになりました。
このまま退職せずにいた場合、10年後の自分がどのように働いているかが、容易に想像できてしまったのです。
長年働いていたこともあり、他部署ともコミュニケーションがとれて社内調整も楽になっていました。
一見すると心地よいのですが、新しい挑戦や学びがない環境は、自分にとって少しずつ“退化”に感じられたのです。
50歳目前で、ふと「このまま10年ここにいても良いのだろうか?」と自問しました。
年収が下がったという要因もありましたが「自分はまだこの先10年バリバリ働きたい、成長し続けられる環境」に身を置きたいと考え、転職を後押ししました。
実際の転職活動では、「その企業で学べること」「新しい領域に関われる可能性」などを、求人票や面接で必ず確認するようにしました。
結果として、これまで経験のなかったITコンサルティングという新しい領域へのチャレンジが決まり、今は未来への手応えを感じています。
読者へのアドバイス
私にとって「安定している=満足」ではありませんでした。何歳になっても「学びたい」という気持ちがある人ほど、転職の選択肢は広がるのではないかと思います。
企業側も、「自走して学び、変化に対応できる人材」を求めている傾向があります。
以下のような視点で、成長機会を見極めると良いでしょう。
- 求人情報に「学習支援制度」「OJT」「社内勉強会」などの記載があるか?
- 面接で即戦力になれることはもちろん「新しい領域に挑戦したい」と伝えたとき、歓迎されるか否か?
- 自分が未経験の業界・職種でも、過去の経験を軸にどう貢献できるかを整理しておく
学び続けられる環境は、年齢に関係なく、自分の未来を前向きに変えていく力になります。
惰性で働くのではなく、“自分で選んだ仕事”として誇れる選択をしていきましょう。
「軸を決めて動き出す」ための5ステップ整理
ここまで「経験」「年収」「将来性」「成長」という4つの視点から転職の軸を掘り下げてきました。
では実際に、私がどのような行動を取ったのか。以下に、転職の軸を固めるための5つのステップを紹介します。
ステップ1. 職務経歴書と履歴書をアップデートする
- 過去の経験を棚卸しし、自分の強みを言語化
- 何にやりがいを感じたのか、何が楽しかったのかを見つめなおす
ステップ2. 転職サイトに登録し、市場を観察
- ビズリーチ、リクルートエージェント、ミドルの転職、doda Xなどに登録
- スカウトや求人の傾向から、市場のニーズや自分の立ち位置・価値を把握
ステップ3. エージェントと面談し、第三者の視点を得る
- 自分では気づかない「評価されるポイント」が見えてくる
- どの職種・業界が自分に合っているか、現実的な道筋を知る
ステップ4. やりたくないことリストを作る(=逆から軸を固める)
- 「もうやりたくないこと」「避けたい職種・環境」を洗い出すことで、自分が目指すべき方向が明確に
ステップ5 . AIと対話しながら、軸と思考を整理する
- 「本当にやりたいことは何?」AIとの壁打ちで客観視&言語化がスムーズに
- 職務経歴書への落とし込みや、面接時の一貫性にもつながる
読者へのアドバイス
「いきなり応募しなければいけない」と思うと気が重くなりがちですが、最初は準備と情報収集で十分です。特に初期のステップとしては:
- 書類を整える
- 転職サイトに登録する
- エージェントと面談してみる
この3つだけで、転職活動は自然と動き出します。
焦らずに「整える → 知る → 考える」の順で進めることで、自分なりの納得感ある方向性が見えてくるはずです。
小さな一歩でも、動き出せば未来は確実に変わっていきます。
まとめ
40〜50代の転職では「何をしたいか分からない」と立ち止まってしまいますが、軸を持てば迷わず動けます。
私は失敗を繰り返しながらですが、失敗を活かしながら「経験・年収・将来・成長」という4つの視点で整理することで、異業種転職を現実的に進められました。
そして学んだのは、自分の希望だけでなく、企業視点を持つことが成功の鍵になるということです。
さらにAIを活用すれば、自分の考えを言語化しやすくなり、次の行動へとつなげやすくなります。
最後に問いかけです。
👉 あなたの転職の軸は、どの視点から始めますか?