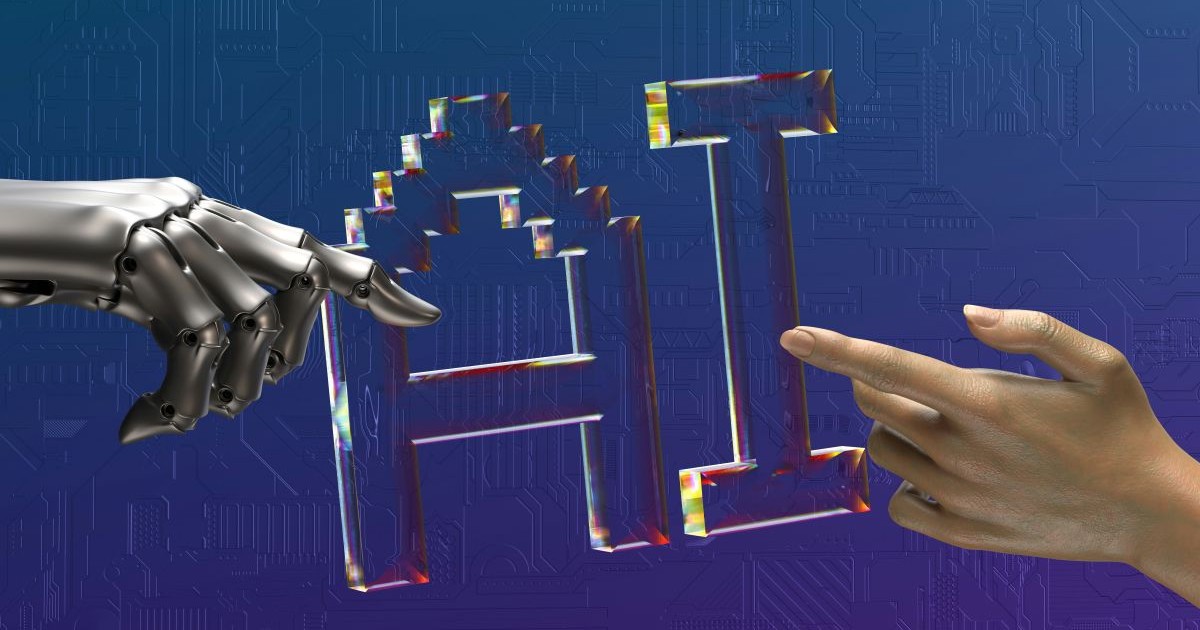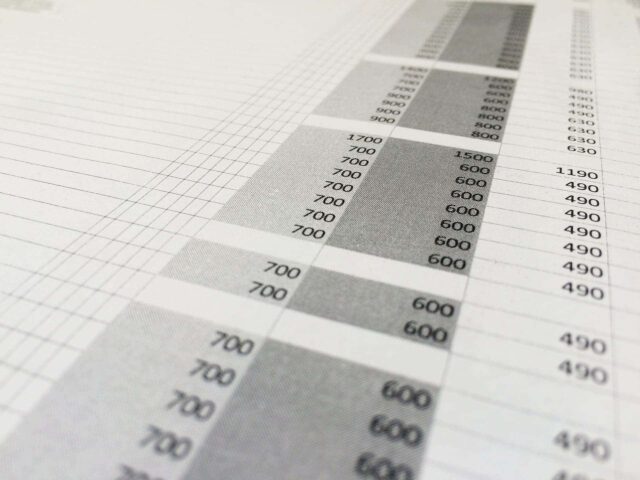- 2023年7月30日
50代の転職活動は、20代・30代とは違った難しさがあります。
これまでの経験をどう活かし、即戦力として働けるのかを問われる一方で、新しい環境に適応する柔軟性も強く求められます。特に、書類の通過率や面接突破は大きなハードルでした。
私自身も転職活動を始めたとき、最初はなかなかうまく進まず苦戦しました。
そんなときに力になってくれたのがAIです。とはいえ、AIにすべてを任せるのではなく、質問に工夫し、AIの回答を鵜吞みにするのではなく“壁打ち相手・整理役”として活用するのがポイントでした。
エージェントのサポートや自分の努力と組み合わせ、AIを第三のパートナーとして取り入れたことで、効率化と精度の両立ができ、納得のいく転職活動を進めることができました。
転職の軸整理 × AI活用|キャリアの方向性を明確に

転職活動の最初にぶつかったのが、「自分はどんな方向性でキャリアを描くのか」という課題でした。
最初は業種を絞らずに動いていたものの、うまくいかず、立ち止まって考え直す必要がありました。
そこでAIを壁打ち相手にして、これまでの経験や価値観を整理しました。
AIに職務経歴書をアップロードしたうえで、
「このキャリアだとどういう職種がある?」
「自分の強みは何か」
「私はこういう時にやりがいを感じるんだけど、どういう職業が向いている?」
といった質問を投げかけると、AIは言葉を整理して返してくれるので、自分一人では気づけなかった視点も得られます。
実際に投げかけた質問の一部はこんな内容です:
•「転職活動で業種や職種を絞ってないんだけど、どういう方法で絞っていくのが良い?」
•「自分の価値観とか、向いている職業などはどうやって見つければよい?」
•「過去、こういうことにやりがいを感じていた」
•「今までは事業会社でのキャリアだったけど、このキャリアを活かして企業支援の会社で働きたい場合、どういう職種がある?」
•「5年後、私はどんなキャリアを歩んでいるべきでしょうか?」
働くうえで不安に思っていたことや、エージェントに相談できないような漠然とした悩みも、AIに投げかけました。
ただ、AIは答えを決めてくれる存在ではありません。
返ってきた内容をそのまま信じるのではなく、「これで良いのか?」「もっと他の可能性は?」と追加で質問して深めていくことで、自分に合った志望動機やキャリアビジョンが形になっていきました。
👉 転職の軸を見つける方法についてはこちらの記事でも詳しく書いています。
書類作成・転職サイト登録 × AI活用|0%から50%以上に改善
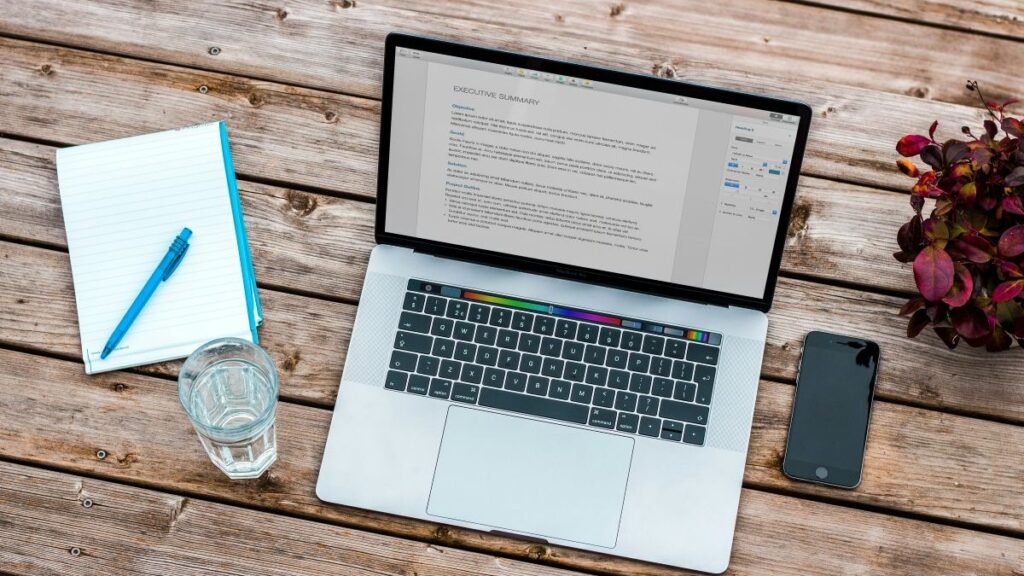
転職活動で最初に直面する大きな壁が「書類通過」です。
特に50代では、ただ経歴を並べるだけでは伝わりにくく、成果や強みを的確に表現することが求められました。
職務経歴書・履歴書の作成は「良いエージェント」と「AI」の両輪で
私はもともと、職務経歴書を定期的にアップデートしていました。
直近の転職は17年前とかなり昔ですが、当時読んだ本に「年に1回は職務経歴書を更新しておくとよい」と書かれていたこともあり、数年に一度は更新してきました。
今回は、その職務経歴書を最新版に直して活動を始めましたが、まったく書類が通過しません…。
最初に相談したエージェントも表面的な修正にとどまり、改善にはつながりませんでした。
転職サイトを見直す中で、ようやく「一緒に職務経歴書を作り込んでくれるエージェント」に出会えたことが大きな転機となりました。
その上でAIには、文章表現のブラッシュアップや体裁の調整を任せ、より読みやすく、自分の強みをしっかりと伝えられる内容に整えることができました。
職務要約・スキルの整理(転職サイト登録用)にAIを活用
転職サイトでは「職務経歴書そのまま」ではなく、要約やスキル欄を簡潔に記入する必要があります。
AIに職務経歴書を読み込ませて要約を生成し、自分が希望する業界・職種を伝えて調整してもらうことで、スカウトされやすい職務要約とスキルが完成しました。
実際にはこんな問いかけをしました:
•「この職種・仕事がしたい。それに合った職務経歴書の要約を作成してください」
•「この職種なら、スキル欄にはどんなワードを入れたら良いか?」
※スキルに書いたことが、検索時に引っかかる
こうしてAIと情報を整理しながら登録内容を整えた結果、スカウトの件数や書類選考の通過率が上がった実感がありました。
転職サイトの選定と調整
また、AIには書類通過で苦戦した結果、登録している転職サイトの見直しを行いました。
「50歳での転職はどのサイトが強い?」「この役職経験、希望年収の場合はどの転職サイトがいい?」「コンサル・システム系の仕事に挑戦したいときは、どういうサイトに登録したらいい?」を相談しました。
リクナビNEXTや通常のdodaよりも、ビズリーチ・dodaX・ミドルの転職といったハイクラス向けサイトが自分には合っている、またコンサルに特化した転職サイトに登録したほうが良いとAIから回答があり、登録する媒体を追加しました。
成果:AI活用で書類通過率が 0% → 50%以上 に改善
最初に使っていたリクナビエージェントでは、数多く応募しても書類通過率は0%。
一方で、AIで職務経歴書やスキルを整え、エージェント・媒体を見直した後は、紹介された求人の通過率は50%以上となりました。
おそらくですが20代・30代が多い求人サイトだと、50代は書類選考が落ちて自信を無くし、自己肯定感を下げるばかりです。
数撃ちゃ当たる方式で失敗した経験から、AIを活かして少数精鋭で挑むスタイルに変えたことが、大きな成果につながったのです。
面接準備 × AI活用|論理的に伝わる力を強化
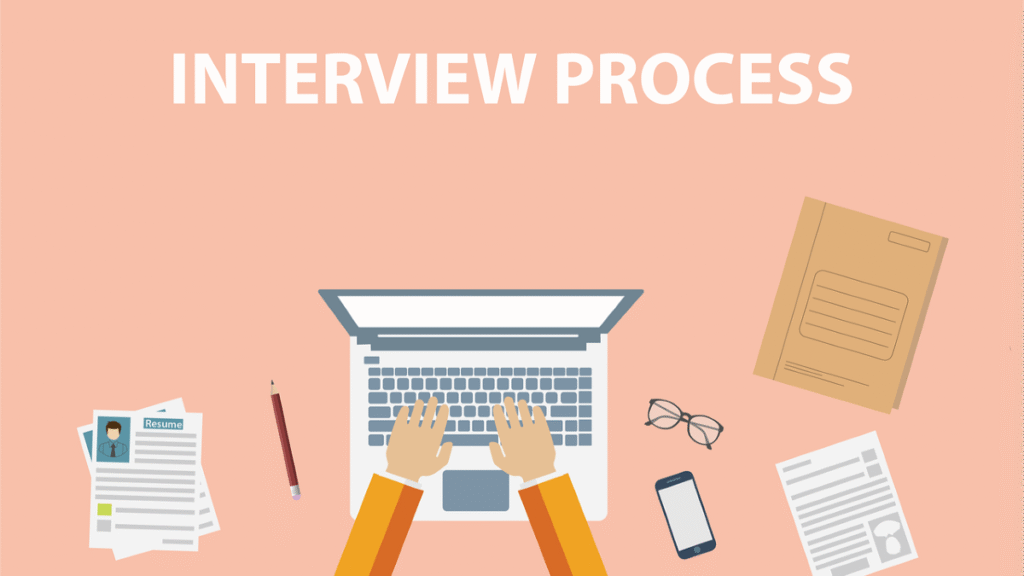
書類を通過した後に待ち構えるのが「面接」です。
50代の転職では、経験を深掘りされる質問やキャリアの方向性に関する問いが多く、事前準備の差が大きく結果に影響しました。
振り返ると、私の転職活動で一番AIを活用し、かつ助けられたと感じたのは、この面接対策だったように思います。
想定質問をAIと一緒に準備
まず取り組んだのは、求人票や職務経歴書をもとに想定質問をAIと一緒に考えることでした。
一般的な想定質問はエージェントからもらえますが、その求人だからこそ聞かれる質問は自分で深掘りする必要があります。
私は面接対策を、書類が通過した企業ごとに1社1社行いました。
各企業の募集要項と自分の職務経歴書をAIに共有し、
「この求人の一次面接で想定される質問は?」「この経歴だと面接官はどんな点を確認しそう?」と相談しながら準備を進めました。
完璧ではありませんが、事前に想定を整理することで、安心感を持って面接に臨めました。
一次面接は通過できても、二次面接で落ちることが続いた時期がありました。
二次面接ではより深くスキルを問われるため、自分の回答が冗長で論理性に欠ける、あるいはスキル不足と見なされることがありました。
実際には経験の横展開で対応できるはずなのに、それをうまく言語化できなかったことが大きな要因でした。
そこで、落ちた面接の質問と回答を毎回すべて整理し、エージェントからのフィードバックを踏まえつつ、AIに「この理由で落ちた場合、どう対策したらよい?」と相談しました。
AIと一緒に分析する中で出てきた改善策が、PREP法で回答を組み立てるという方法でした。
PREP法での回答練習
AIには過去の質問を読み込ませ、さらに追加の想定質問も考えてもらいながら、PREP法で回答を整理しました。
実際の質問(例:「なぜコンサルに挑戦するのですか?」)を題材に、AIと壁打ちした回答は次のような流れです。
P(Point)結論(要点): 「私はこれまでの経験を活かし、コンサルタントとして多くの企業を支援したいと考えています。」
R(Reason)理由: 「事業会社で培った新規事業立ち上げや業務改善の経験が、クライアントの課題解決に役立つからです。」
E(Example)具体例: 「例えば、EC事業では物流システム移管プロジェクトをリードし、業務効率を大幅に改善しました。」
P(Point)再度、結論: 「このように、これまでの経験を広く活かせる場として、私はコンサルに挑戦したいのです。」
※PREP法の詳細は リクナビNEXTの解説ページ でも紹介されています
PREP法で回答を整理し、AIと何度も練習を繰り返すことで、冗長になりがちな答えを短時間で論理的に話せるようになりました。
本番の面接でも落ち着いて回答でき、「話が分かりやすい」と面接官から評価されました。
※PREP法とは、ビジネスや面接、プレゼンなどで「わかりやすく・論理的に・簡潔に」話すためのフレームワークです。
P(結論)→R(理由)→E(具体例)→P(結論)の順で答えることで、説得力のある話し方ができます。
今回は「なぜコンサルに挑戦するのか?」を例にしましたが、この方法はどんな職種・質問でも応用可能です。
「なぜこの会社なのか?」「あなたの強みは?」といった定番の質問にも効果的です。
逆質問をAIと一緒に準備
さらに、面接の最後に必ず聞かれる「何か質問はありますか?」もAIと一緒に考えました。
「この会社のビジョンを踏まえた逆質問は?」「候補者として前向きに見える逆質問は?」と相談し、複数の候補を準備。
結果として「きちんと調べてきている」と好印象を持たれるきっかけになったと感じます。
この章のポイントまとめ
• 想定質問はAIと一緒に考えて安心感を得た
• 一次面接で落ちた経験をAIと振り返り、改善点を整理した
• PREP法で回答を組み立て、論理的に伝えられるようになった
• 逆質問もAIと準備し、前向きな姿勢をアピールできた
提出課題・企画書 × AI活用|抽象から具体へ落とし込む力

企業によりますが、最終面接では社長・役員面接や、面接だけではなく課題作成を行うケースもあります。
私が受けた企業でも課題の提出課題があり、これは転職活動の大きな山場のひとつでした。
構成を考えるのは自分、整理と具体化はAIと一緒に
最初に大枠の構成や流れは自分で考えました。
「現状 → 課題 → 解決策」という骨子を描き、課題に対して自分の考えを箇条書きでAIに共有。
「どうまとめるとよい?」「ここの根拠は?」「別の視点から見るとどう考えられる?」と相談しながら、何度も壁打ちを繰り返しました。
抽象的になりがちなAIのアウトプットを修正
AIと一緒に整理するとスッキリまとまる一方で、どうしても抽象的な表現に偏りがちでした。
実際、エージェントに見せたところ「抽象的すぎる」と指摘を受けています。
AIはどうしても「ふんわりした耳障りのよい言葉」を使いがちだと感じます。
そこでAIに何度も問いかけました:
•「この言い回しは抽象的だから、具体的に置き換えるとどうなる?」
•「実行手順として表現するならどうなる?」
•「未来の姿をわかりやすく表現するなら?」
こうしたやり取りを重ねることで、抽象的な表現を具体的な施策やステップに落とし込めました。
AIの提案をそのまま使うのではなく、自分の言葉に置き換え、さらにエージェントの視点を取り入れる。
この「自分 → AI → エージェント → 再びAI」の繰り返しが完成度を高めるカギでした。
また、私は基本的にChatGPTの有料版を使っていましたが、Copilotや他のAIにも同じ質問を投げ、回答の違いを見ることもしていました。
成果
最終的に仕上がった提出物は「論理性」と「具体性」を兼ね備え、自信を持って提出できました。
AIと一緒に作り込む過程で、「自分の言葉でしっかり説明できるか?」「実際の業務経験に置き換えて話せるか?」を常に意識するようになり、結果的にプレゼン練習にもつながりました。
緊張はしましたが、面接官からは「わかりやすい提案だった」と評価を受け、この課題を乗り越えられたことは大きな自信につながりました。
最終的に感じたのは、AIだけで完結するものではないということです。
AIは壁打ち相手としてとても心強い存在ですが、ときに表現が抽象的にまとまることがあります。
だからこそ、エージェント(人)の視点+AIの整理力+自分の判断を組み合わせることで、提出課題をより具体的で説得力のあるものに仕上げられました。
AIは「すべてを任せる代行者」ではなく、「一緒に考えるパートナー」だと実感しました。
まとめ
AIは万能ではありませんが、「壁打ち相手・整理役」として取り入れることで、50代の転職活動に大きな力を発揮しました。
書類・面接・企画書・キャリア整理まで、AIを活用することで効率化と精度を両立できたのです。
大切なのは 「人(自分+エージェント)× AI」 の組み合わせ。
経験を持つ50代だからこそ、AIを第三のパートナーとして迎えることで、新しいキャリアへの道が開けるのだと思います。
🔗 参考リンク
-
50代でも迷わない!転職の軸を見つける方法
記事がありません